|
Wagner Ring Walkure
愛知祝祭管弦楽団のワルキューレを聴いて |
音楽は人間と同じくらい昔から存在したと思う。
森のなかに建っている我が家は毎春、求愛する小鳥たちの歌声に包まれる。そんな姿を見て彼らの音楽を聴いていると、言葉を持つ遥か以前から人間は音楽を持っていたと信じられる。だから音楽には、聴く喜びも演奏する喜びも、どちらも同じくらいあると思う。それらに付け加えて、音楽を語る喜びも、同じくらいあるに違いない。
最初から少し脱線して申し訳ないが、30才くらいまでわたしは良くピアノを弾き、時々は作曲もした。
レコードを聴いて感動すると、その曲について親しい友人たちと語り合った。
今から振り返ってみると、この時、音楽や文学について友と語り合ったことが、自分の人間性を形成するうえで、とても大きな意味を持っていたことがわかる。
そんな友人たちとの語らいで、こんな風に感じたことがある。
「とても話しやすい曲と、なかなか話しづらい曲がある。それだけでなく、話したくない曲や、秘密にしておきたい曲すらある」
モーツァルトの名曲についてなら、いとも簡単に口にできた。
ベートーヴェンの中期までなら、こちらも躊躇なく口にできた。
ところが、マーラーの 『大地の歌』 やベートーヴェンの後期についてはなかなか口にできなかった。特に 『大地の歌』 の告別や交響曲第9番については、自分だけのものにしておきたいという気持ちや、話してはいけないのではないか・・・という気持ちすら持っていた。
愛知祝祭管弦楽団のワルキューレは、そんな 「話せない」 、または 「話したくない」 感動の延長線上にある。
どこまで話せるのか。それも、大きな疑問である。
演奏会が終わった直後、指揮者であり親友でもある三澤洋史君と逢ったが、簡単でごくあたりまえな 「素晴らしかったよ」 としか言えなかった。
そのあとコンサートマスターの高橋広君と逢った時、わたしは少し彼から離れていたいとすら感じた。
どちらにしてもわたしにとって、これは巨大な音楽体験であり、その震動が今でも続いている演奏会であったことは確かである。
このオーケストラを初めて聴いたのは7年前となる2010年だった。プログラムはマーラーの4番と 『トリスタンとイゾルデ』 の抜粋というもの。『トリスタンとイゾルデ』
は抜粋という枠を超えるほど大きな規模だった。
この時わたしを惹きつけたのは、ワルキューレでもコンサートマスターを務めた高橋君の演奏である。特に本番直前のリハーサルにおける2楽章のソロに強く惹きつけられた。
「こんな表現ができる演奏家が、日本のこんな身近にいるなんて」
鳥肌が立った。

オーケストラ全体のレベルはしかし、まだアマチュアという言葉がふさわしいものだったかもしれない。
ところがマーラー4番の3楽章で、三澤洋史の意図するところを完全に理解し、それを実現させようとする大きなエネルギーを感じさせてくれたのも事実だった。実際に実現できたとは言えないが、明確なヴィジョンを見せてくれた。そのヴィジョンは素晴らしく、プロの一流オーケストラでもなかなかできないことだと信じられた。
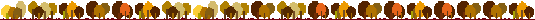
わたしはもう60才を超えている。
だから、育ったのはレコード時代である。
特にわたしをクラシック好きに育てたのは、音楽好きな両親であり、母が所蔵するたくさんのSPレコードだった。そのため音は耳でなく、心で聴く習慣が付いている。なぜなら72回転のモノラルレコードから聞こえてきたのは、ほとんどが雑音であり、針の摩擦音だったから。
心のなかで雑音を取り払い、音の美しさを補い、音の強弱やバランスを補ってはじめて音楽が聴こえてきたように思う。つまり想像力がなければ、音楽は心に入ってこなかったのだ。
そんな聴き方をしてきたら、奏でている音楽の向こうに理想があるか否かが聴こえてくるようになった。いつもではないが、時々彼らの理想とする音楽が聴こえてくる。
また指揮者が今創造している音楽に満足しているのか、それとももっと高みに理想を持ち、それに向かって音楽を創っているのかを感じられるようになった。
この時、マーラー4番の三楽章から、高く美しい理想が聴こえてきた。
「今はこんな音楽だけれど、ほんとうはこうしたい」 というヴィジョンが明確に伝わってきた。そこに提示された音楽は、これまで聴いたどんな4番よりも素晴らしいと感じられるもので、それに心底魅了された。
この時、オーケストラから発せられる音楽の理想に心を乗っ取られた。取り憑かれたと言ってもいい。
そんな2010年から三澤洋史とオーケストラは急速に緊密さを増し、進化を続けてきた。誰が聴いても分かるようなミスが激減し、各パートのソロがしっかり歌うようになってきた。
それまで異常に突出していたコンサートマスターのヴァイオリンの音が、大きな音の流れに調和するようになった。
特筆すべきは 『パルジファル』 だろう。
ここにおいて、オーケストラは三澤洋史だけの音を実現したように感じたのだから。
極端な言い方をするなら、わたしは三澤洋史公認の世界初、かつ世界一のファンである。彼を音楽家にするため、自分なりにずいぶんいろいろな手を打ってきたと思う。
だから彼の理想の音楽なら、一般のみなさんよりは知っている・・・・と信じている。加えて彼の音楽の根底に流れているものは、知り合っていらい変わっていないとも信じられる。
そんな三澤洋史の音を、オーケストラが形にするようになり、そんな過程で 『ラインの黄金』 が挙行されることになった。
以下、昨年の音楽会後に書いた文章からの引用である。

わたしたちは高校生の頃、よくワーグナーやバイロイトについて語り合った。
「いつかバイロイトで、本物のワーグナーを聴きたい」 と夢を語り合った。
あれから年月を経て、彼はバイロイトで実際の指揮を実現し、ついに日本でリングを演奏する時を迎えた。
かつて彼が好んだワーグナーは、何と言っても パルジファル だった。
いっぽうのわたしは、何と言っても トリスタンとイゾルデ だった。
これは今でも変わっていない。
当時は二人とも、『リング』 をそれほど評価していなかった。それはリングのストーリーに、強烈に心を打つ何かを認めなかったからである。
たぶん三澤洋史による演奏会がなければ、わたしが真剣にリングを聴くことなどなかったかもしれない。20代における理解から、わたしのリングは先に進まなかったかもしれない。しかし、彼が演奏するということで、古くから持っているショルティ盤を聴き直し、DVDを購入して予習した。
その過程で、「ワーグナーならやはり トリスタン だ」 という想いが再発していた。
しかし・・・・・・。
彼の振る本番に、魔法が下りたのである。
むなしいストーリーにもかかわらず、魔法が掛かったのだ。
登場人物に誰一人、尊敬できる人はいない。下劣で、自分勝手な人間(神々)ばかりが、エゴと欲望をぶつけ合う。そんな世界が、異常に心に食い入ってきた。
それは、まるで現代の世界情勢でもあるかのように、現実の問題として、わたしの心に食い入ってきたのである。
気が付くと、まわりの観衆たちも、息を殺して音楽に集中していた。
音楽を命のように呼吸しているのが、手に取るように感じられた。
オーケストラと歌手たちが、音楽に没入し、自分たちを表現しているだけでなく、それが聴衆の心に届き、掴んで離さない 『場』 が劇場全体を包み始めていた。
第4場になると聴衆のエネルギーが、指揮する彼を通してオーケストラに環流し、そこで圧倒的な力に増幅され、ふたたび吹き出してくるようにすら感じられた。
彼の指揮も、後半になればなるほど生命が宿り、躍動した。
特別な空間が生み出され、劇場全体が特別な場となった。

そして、今年のワルキューレを迎えることになる。
本番の二週間前、わたしは彼らの練習を聴きに行った。
到着するなりステージに上げていただき、日本を代表するワーグナー歌手の皆さんを間近で聴くことができた。歌手の皆さんには圧倒されたものの、オーケストラから響いてくる音には、正直危機感を覚えたことを書いておこう。
それまでのオーケストラより、良くなったと感じたのはチェロのみ。それ以外は、まだまだ音すら取れていない方もいると感じてしまったのである。
もちろん、音楽そのものが技術的に難しいことは知っているし、アマチュアが挑戦すること自体が冒険ということも承知している。そして団員全員が、部外者のわたしたちを温かく迎えてくださることも知っている・・・ほんとうにありがとうございます。
しかしもう、たった二週間しか残されていないのだ。
もしわたしが三澤洋史だったなら、強い恐怖を感じたかもしれない。
だから、とても不安な気持ちで会場入りをした。
ふだんならリハーサルから聴くのだが、この日は自分のスケジュールと体調もあって、本番のみの鑑賞となった。
9月11日の 『ラインの黄金』 から6月11日の 『ワルキューレ』 まで正味9ヶ月。
しかも、『ラインの黄金』 より圧倒的に長く難しいワルキューレである。
公演から二週間が経った今なら、笑顔で 「ギリギリだったね」 とか 「薄氷を踏むようだったね」 とか表現することができる。
しかし本番最中は彼らの意気込みと熱気、そして彼らのヴィジョンに圧倒され続けた。もちろん細かいミスや失敗はあったのだろう。しかし、それはわたしには聴こえてこなかった。
三澤洋史と彼らのヴィジョンが、圧倒的な存在となり、演奏会場を満たしたのである。
加えて、それを環流させる観衆のエネルギーも素晴らしかった。
二幕を終えた演奏者たちの顔を見て、自然に涙が溢れてきた。
どんな二週間を、彼らはすごしたのだろう。
想像に難くなかった。

二幕と三幕は、ワーグナーの演奏史上でも特筆すべきものだったに違いない。
テンポ設定にしても主張すべき音楽にしても、ワーグナーが過去の遺産でなく、今現在の人間にとって必要不可欠な音楽であることをまざまざと知らせてくれる演奏だったから。
『リング』 などたいしたことのない作品だと思っていたわたしは、文字通りこの演奏に殴りつけられたのだ。
人間(神々)の心は大昔から変わっていず、いつの時代でも同じ問題を抱え、それに振り回されていることを痛感させられた。
演奏会が終わると、SNSにたくさんの声が寄せられた。
これほど多くの言葉が寄せられた演奏会も、珍しい。それどころか存在しないのではないだろうか。それらの中には、わたしなど到底及ばない素晴らしい意見がたくさんあった。
なかからこんなツイートを一つ。
「オケのメンバーが入場してくる時の、まなじりの決し方が個人観劇史上最高。そこで涙腺決壊して、最後まで。音楽は人がやるもの、を再認識」
音楽にはさまざまな楽しみ方がある。
ただ、演奏する人たちに感動がなければ、それは観客には伝わらないのではないだろうか。作曲者の意図がうんぬん云われるが、演奏する人たちがその音楽に没入し、それに感動できなければ、伝わる音も本物の感動とならず、聴き手に届かないのではないだろうか。
加えて、彼らの感動と理解のレベルが、そのまま音楽に乗って伝わることも事実だろう。
そう考えると愛知祝祭管弦楽団は、世界一感動しながら演奏するオーケストラである。
演奏家の感動が、自分の心に直截に流れ込んでくるオーケストラであり、彼らの音楽に対する愛情が、直接伝わってくる団体である。
演奏会が終わって、わたしは言葉が出てこなかった。
圧倒された。
間違いなく 「素晴らしかった」 ので、かろうじてそれだけを親友に伝えると、それ以上詳しい感想を口にできなかった。
そんな中、尊敬するマーラー研究者の前島先生が、コンサートマスターの高橋君と握手を交わしたとたん涙するその姿に、もう一度こみ上げてくるものがあった。それは前島先生もわたしと同じように、彼らの感動を共有していたことを教えてくれたからだ。
来年の 『ジークフリート』 は9月2日である。
すでにジークフリートの練習はスタートを切り、全員が大いなるエネルギーを注ぎ込みはじめている。
18世紀から20世紀にかけ、ヨーロッパに成長したクラシック音楽が、こんな形で日本でおこなわれ、実現している姿を、ワーグナーはどう思っているのだろう。ベートーヴェンはどう思っているのだろう。
ほんとうに素晴らしいものが、世界共通のものに育っていく過程を、わたしたちはこの愛知祝祭管弦楽団と三澤洋史から教えてもらっている。
世界一の感動を伝えてくれる世界一おもしろい管弦楽団が、現代の日本にある。
彼らにとってクラシック音楽は過去の遺産でなく、今現在の彼らにとって必要なもので、人生を豊かにし、自分の人間性を磨くものとなっている。
そんな姿にわたし自身、身の引き締まる思いがする。
愛知祝祭管弦楽団のみなさん、そして素晴らしい歌手のみなさん、ほんとうにありがとうございました。
そして、親友の三澤洋史に心からの感謝を。
47年前に夢を語った君が指揮をし、そこから限りない感動を得るという体験。
それはわたしの人生にとって最高の宝の一つです。
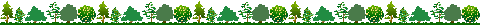
最後に、わたしが知ったツイッターのいくつかを記しておこう。
まだまだあるだろうから、もし良いツイートを知っている方は知らせて欲しい。
ここに追加させてもらいたいから。
「愛知祝祭のワルキューレを観劇。ホールの響きも良くオケも三澤氏の棒に応え熱演!歌手は清水華澄さんの感情表現力と青山貴氏の堂々たる演技に感服!特に2幕後半〜3幕は圧巻!!演出も工夫され、決してワグネリアンでない私もあっという間の5時間を堪能。スタッフの皆様にも感謝の一夜でした」
「昨日の愛知祝祭管弦楽団のワルキューレ公演をきいてから、身体絶好調!すべてにおいてすばらしく、私の全身は癒やされた。あたたかい人たちのエネルギー最高!」
「3幕で泣くことはあったけれど、1幕、2幕と泣かされたのは初めてでした」
「全国区の青山ヴォータンと清水ジークリンデに対し、一歩も引かなかった地元の基村ブリュンヒルデ、3人が繰り広げる丁々発止の"歌合戦"は聴き応え満点。そしてそれを支えた三澤率いるオケの健闘見事。興奮未だ醒めず」
|
|


