| Masahito's Musical Essay This is a page for Beethoven わたしの魂を支えるもの |
ベートーヴェンについて語ること。  それはわたしがもっともやってみたいことであり、かつもっとも難しいことでもあります。 小さな頃からいったい、どれくらいベートーヴェンを想ったでしょうか。そして、どれくらいベートーヴェンという偶像に、さまざまな問いを投げかけたことでしょうか。 この世の誰もが答えを出せないと感じたとき、わたしはベートーヴェンに助けを求めました。 この世に生きているいないに関わらず、わたしが成長する過程で、もっとも強い影響を受けたのはベートーヴェンに違いありません。 こうした気持ちをもった人間は実はわたしだけではなく、たくさんの方たちがそんな気持ちを残しています。そのため、こうした人たちとあたかも兄弟であるかのような感情さえ芽生えてきました。たとえば、『ベートーヴェンの生涯』という美しい本の中で、ロマン・ロランは次のような鮮烈な気持ちを吐露しています。 ……。雨しげき四月の灰色の日々に、霧に包まれたラインの川辺で、ただベートーヴェンとだけ、心の中で語り合い、彼に自分の思いを告白し、彼の悲しみと彼の雄々しさと、彼の悩みと彼の歓喜とによってまったく心を浸され、ひざまずいている心は、彼の手によって再び立ちあがらされた。 わたしも何度となく、このロランのような気持ちになりました。 高校生の時、わたしは悩みから授業をさぼり、近くを流れる烏川の畔をさまよい、観音山の深い森にわけ入った記憶があります。あの頃はまだ、ロランの『ベートーヴェンの生涯』を知りませんでしたが、ロランと同じように、わたしは人生の答えを…人はなぜ生きるのか…という根本的問題を、ベートーヴェンに求め続けたのです。 わたしにとって、ベートーヴェンが成功のうちにではなく、失意と貧困のうちに亡くなったこと。それはどこかで慰めとなっていました。特に思春期には、それが大きな力になってくれたのです。 「あれほど素晴らしい音楽家の最後が、いたくみすぼらしかった」 そんな事実に、後ろめたい嬉しさを感じていました。 「誰も理解してくれない』と感じていたわたしの孤独が…まだ世間知らずで空想的な青年の孤独が…、どこかでベートーヴェンの音楽や人生と共鳴しているかのように感じられたのです。 十代で聴いたベートーヴェンの思い出は交響曲の数々です。 とても苦しかった高校時代、わたしは4番、5番、7番を聴き続けました。 そんな頃、次のような出来事がありました。 それは数学の授業中でしたが、突然「こんな学校教育を受けていると、自分はダメになってしまう」と、強烈に感じたのです。しかし、なぜそんな風に感じたのか、それがどれくらい論理的根拠を持っているのか、わたしには理解できませんでした。ただそれ以来、学校教育を信じることができなくなり、結果、勉強にエネルギーを費やすこともできなくなり、みんなから離脱していくような孤独感を感じ始めたのです。そして、苦しく、孤独な日々の連続に、捕らえられるようになりました。 このころ、ひとつ興味深い思い出があります。それは弦楽四重奏16番にかかわる思い出です。 「ベートーヴェン最後の曲」「哲学的な深さと謎に包まれる曲」などと伝えられている弦楽四重奏を、わたしはレコードショップの輸入廉価版で買ってきました。確かソビエトのベートーヴェン四重奏団のレコードだったように記憶しています。 一家みんなが寝静まった頃、ヘッドホーンを付け、緊張しながらレコードに針を下ろしました。当時、新しいレコードに針を降ろす行為はわたしにとって、もっともわくわくするできごとでした。 ところが、この四重奏曲を、わたしはまったく理解できなかったのです。 聴いているうちに、まるで嫌なジョークを聴いたかのような気持ちになりました。 『あのベートーヴェンが、わたしの英雄ベートーヴェンが、こんな曲を最後に創ったなんて…』 わたしはがっかりするどころか、怒りさえ感じました。 その後、しばらくベートーヴェンを聴かなかったほど、わたしには理解できませんでした。しかし、そうこうしているうち、ふたたび中期のピアノソナタに取り憑かれ、不可解な弦楽四重奏曲のことは忘れ去られたのです。  二十代前半のわたしはひたすらピアノ曲を聴き続けました。そして聴けば聴くほど、ピアニストにならなかったことを悔やむようになりました。 二十代前半のわたしはひたすらピアノ曲を聴き続けました。そして聴けば聴くほど、ピアニストにならなかったことを悔やむようになりました。たぶん、もっともたくさん聴いたのは8番の悲愴ソナタでしょうか。ケンプとバックハウスからはじまり、手に入るほとんどのレコードを聴きました。お気に入りはエンジェルレコードから出ていたエッシェンバッハのものです。当時、エッシェンバッハの悲愴ソナタはグラモフォンからも出ていましたが、わたしは過激なエンジェル盤が好きでたまりませんでした。 悲愴ソナタの次に聴いたのは28番と31番でしょう。これもずいぶんケンプとバックハウスで聴き込みました。その後、ゼルキンのレコードを好きになり、それこそすり切れるほどに聴きました。まだCDのない時代、同じレコードをもう一枚買おうかと悩むほど、ゼルキン盤を聴き続けました。 二十代の半ばに、スキーで大きな怪我に見舞われた時、わたしはいきなりブラームスの音楽に目覚めました。それまで嫌いだったブラームスが、大好きになりました。そして、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第七番のアダージョに深く感激した記憶も残っています。 三十代に、わたしはあまりクラシック音楽に没頭しませんでした。 仕事が忙しく、生活に追われていたことや、さまざまな出来事の連続で、落ち着いて音楽を聴く時間がなかったのです。 この頃の音楽の思い出としては、ハイドンやモーツアルト初期のピアノソナタを聴きながら、原稿を書き続けたこと。それからグレン・グールドのバッハに感動したことくらいです。 あまりバッハを聴いたことのなかったわたしですが、グールドのバッハは心の深いところに染み入ってきました。そこから彼の世界が広がり、生まれて初めてハイドンやモーツアルトのピアノソナタに興味をそそられました。しかし、この時期の音楽はバックグラウンド・ミュージックに近い聴き方をすることが多く、高校生や大学生、スキーで生活をはじめたばかりの頃のように、生きるためどうしても必要な栄養として聴かれていたわけではありません。 もう一度、真剣に音楽を聴くようになったのは白馬に移り、四十才にもなろうという頃です。 その再スタートとなったのはマーラーでした。十代の頃、十分な理解もできないまま、心のどこかでひかれていたマーラーの音楽が、初めて自分自身の言葉となり、実体験としてわたしをとらえたのです。 これほど夢中になって音楽を聴いたのは高校生以来のことでした。 毎夜毎夜、わたしはベッドに横たわり、ヘッドホーンでマーラーを聴き続けました。最初に夢中になったのはテンシュタットの全集です。それからショルティを聴き、シノーポリ、インバルと続きました。 この時に強い感銘を受けた演奏に、次のようなものがあります。 まず、第1番の演奏としてテンシュタットのシカゴ盤。この指揮者の音楽は決して美しくありません。しかし、このシカゴ盤はわたしの心をとらえて離さないのです。 2番から1枚を選ぶのは難しいことです。たくさんの素晴らしい演奏がありますが、ここではあえて、小澤征爾盤を上げておきましょう。この2番とブラームスの交響曲集はわたしの好きな小澤さんのCDです。自分がいちばんよく聴く2番はショルティですが…。 6番こそ、この時期のわたしがもっとも取り憑かれた曲です。ほんとうにたくさんのCDを買いました。いちばん聴いたのはカラヤンでしょうか。またショルティ盤もたくさん聴きました。ずいぶん異なった性格を持っていますが、どちらの演奏も好きなものです。 9番はバルビローリとカラヤン(ライブ盤)を上げておきましょう。ほんとうに奥深い音楽です。 このマーラー熱がすぎると驚いたことに、間髪をいれずワグナー熱に冒されました。リングの全曲を続けざまに何度も聴きました。そのため、いつも寝不足でした。また、わたしの大好きな「トリスタンとイゾルデ」のCDに、ずいぶん出費しました。それまでわたしは「トリスタン」を、大学時代に買ったベームのレコードしか持っていませんでした。しかし、レコードプレーヤーを持っていない現在、それを聴くことはできません。そこで、同じベームのCDを買ったことが、長く続くワーグナー熱再発のきっかけとなりました。この頃、親友の三澤洋史君がバイロイトにて合唱指揮をおこなったことも熱病に油を注ぐ原因となりました。 トリスタンの全曲はフルトベングラー、カラヤンと続き、バレンボイム盤を購入。このあたりから、中古CDショップに出入りするようになりました。東京に行くたび、神田を歩きました。趣味が読書と音楽鑑賞のため、両者共に神田が素晴らしい場所を提供してくれました。 ワグナー熱が過ぎ去り、一段落すると、不思議なことが起こりはじめました。 強く室内楽にひかれたのです。 十五才くらいから、時に室内楽を聴いてきました。しかし、ピアノが入ったもの以外、あまり感動した記憶はありません。ところが、あの膝の怪我の時以来、初めてベートーヴェンの弦楽四重奏にとらえられたのです。 きっかけはアルバン・ベルク四重奏団のベートーヴェン1番でした。 なぜかこの演奏に引きつけられ、次々と聴いていったのです。 1、2、3番と聴き、やがて中期、後期と聴いていった時のこと…。 不思議な想いと共に、思い出の16番を聴くことになりました。 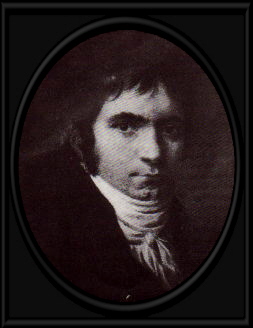 十六才以来、一度も聴いていなかった曲です。演奏はアルバン・ベルク弦楽四重奏団。彼らの演奏は現在二種類ありますが、あの時聴いたのはスタジオ録音盤ではない、新しいライブ盤の方でした。 冒頭から、すぐに音楽に引き込まれました。そして若かった頃、不可解に感じたパッセージや響きが、すべて意味を持って聞こえてきたのです。 この頃、わたしはステレオを寝室に持ち込んでいました。それまで仕事部屋にあったものを寝室へ運んだため、ヘッドホーンではなく、直接スピーカーから聴くことができるようになっていました。 わたしの家は白馬にあり、静かな森の中にあります。そんな静寂に16番が響いたとき、そこに驚きが待っていました。かつて聴いた訳のわからなかった曲が、いつの間にか、もっとも身近に感じられる曲へと変わっていたのです。 3楽章がはじまると、心が震えました。涙が流れ、それは楽章が終わるまで、とぎれることがありませんでした。 いったい、ベートーヴェンの晩年はどんなものだったのでしょう。わたしはその深さと意義に想いを寄せざるをえません。 わたしがベートーヴェン後期を理解するために支払ったもの。それは、気の遠くなるような苦痛と、孤独、そして悲しみでした。それらを経験してはじめて、ベートーヴェンの後期はわたしに扉を開いてくれたのです。 そこには限りない慰めと寂々たる世界があります。 そこでは闘いの人だったベートーヴェンが、「和」をまさぐっているようです。現世的な理想家だったベートーヴェンが、あたかも老子のような精神世界をさまよっています。 ベートーヴェン後期に共感すること。それは人間にとって、どんな意味を持つのでしょうか。 ベートーヴェン「闘いの軌跡」という本の中で、井上和雄氏はベートーヴェンの晩年を精神の崩壊、不安定さという観点から語っています。かつてのわたしなら、特に高校生のわたしなら、この観点と解釈に、誰よりも賛同したに違いありません。しかし、スキー選手として2度の挫折を味わい、ビジネスマンとして何度もの危機をくぐり抜け、ついに人間としての危機にすら直面して、わたしのベートーヴェンはようやくほんとうの言葉を語りはじめたように感じられてならないのです。 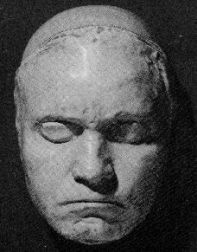 12番から16番までの弦楽四重奏の世界は後期のピアノソナタですら到達しえなかった高みにあります。それらはあまりの高みにあるがゆえ、ほとんどの人間の共感を超えていると言えるかもしれません。それは孤高にあり、誰しもの、誰でもの理解や共感を拒否しています。しかし、そこに達することができたなら、限りない慰めと喜びに満ちています。 果たして、その世界を理解することは人間にとって幸福なのでしょうか。 もしかしたら、人間はそれほどの孤独や悲しみを知らないほうがよいのではないでしょうか。それどころか、いったいどれほどの人間が、そんな孤独や悲しみに耐えられるでしょうか。 そんな気持ちすらわいてくるこのごろです。 わたしが若者だった頃選んだ人生の師であるベートーヴェンが、今でも新しい教えを垂れてくれることに、驚きと共に、心からの感謝を捧げたいと思います。 |
| 音楽のトップページへ | |
| ホームへ戻る |